 |
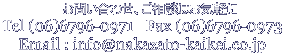 |
 |
||||||||
 |
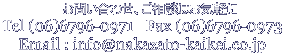 |
 |
||||||||


| 継続的に対価を得て、継続的に事業を行う人 |
| 事業は農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、卸売および小売業(飲食店業含む)、金融保険業、不動産業、運輸通信業、医業、著述業などに分類されます。 |
|
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入金額と必要経費金額の計上 | |
| 事業所得の金額の計算上、1年間に生じた収入金額をもれなく計上しなければなりません。原則としてその収入金額は現金をもらった時点ではなく、現金をもらえることが確定した時点で認識しなければなりません。したがって12月31日に売上の請求書を発行して、その入金が翌年1月以降になる場合でも収入として計上しなければなりません。その場合には帳簿では売掛金・未収金で認識することになります。一方で必要経費においても12月に請求書を受け取り、その支払いが1月以降になる場合においても、その請求書に対する金額はその年の必要経費に計上することになります。 |
| 気をつければいけない収入金額 | |
| 事業を営んでいる人でも、本来の事業以外の収入を得ることもあるはずです。例えば、小売業を営んでいる人がお店にあるものを自宅で使用してしまった場合や、事業で使っていた自動車を売却してしまったなどのケースです。また、事業用の預貯金について預金利息を受け取る場合もあるでしょう。 まず小売業を営んでいる人がお店のものを自宅用にしてしまった場合(自家消費)、これはお店がその事業を営んでいる人に売り上げたということになります。したがって原則は、自家消費したものの販売価額を収入に計上しなければなりません。ただし、その自家消費した資産の仕入れ価額以上の金額(仕入れ価額が販売価額の70%相当額未満である場合には70%に相当する金額)を収入金額として記帳している場合には、その金額も認められます。そのため自家消費した場合でもきちんと記帳していくことが重要です。 次に事業の用に使用している自動車を売却した場合ですが、事業で使用しているため事業所得に算入すべきと思われがちですが、これは譲渡所得として事業所得とは別に所得を計算することとなります。 また、預金利息については原則源泉分離課税が適用され、利息を受け取った時点で税金が控除されているため事業所得の収入金額には含めません。 |
| 気をつければいけならない必要経費 |
|
| 必要経費とは収入金額を得るために支出したもので仕入、通信費、旅費交通費、租税公課等さまざまなものが含まれます。この中でも気をつけなければならない必要経費、自宅と事業所を兼用している人の水道光熱費、電話代、固定資産税、家賃等です。 自宅と事業所を兼用している場合には事業で使用している部分と自宅で使用した部分を区分しなければなりません。事業で使用している部分については必要経費に算入できます。ここで気をつけなければならないのは、自宅使用部分と事業用部分を合理的に区分しなければならないことです。家賃や固定資産税については面積を自宅部分と事業部分で按分する方法が妥当であると考えられますが、水道光熱費、電話代については使用時間や使用頻度を参考に区分しなければなりません。 |
| 必要経費にできない支出 |
| ● | 所得税、住民税:所得に対して計算する税金であるため必要経費にはなりません。 | |
| ● | 国民健康保険料、国民年金保険料:社会保険料控除の対象であるため必要経費にはなりません。 | |
| ● | 個人で加入した生命保険料、損害保険料:生命保険料控除、損害保険料控除の対象となるため必要経費にはなりません。 |
| 青色申告にした場合の得点 |
|
|
事業所得のある人は青色申告か白色申告で確定申告することになります。青色申告にすることによってさまざまな特典が受けられます。そのためには、きちんと帳簿を記帳し、備えつける必要があり、正規の簿記の原則により記帳しているかどうかによって、控除額が変わってきます(下記の「青色申告特別控除」参照)。 |
|
| ● | 青色申告特別控除 | |
| 事業所得の金額にかかる取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。 また、正規の簿記の原則によらず簡易的に帳簿を記帳している場合には10万円を控除することを認めるというものです。 |
||
| ● | 青色事業専従者給与 | |
| 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限内に提出した場合には配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与を届出書に記載された金額の範囲内で専従者の給与として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。 なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 |
||
| ● | 貸倒引当金 | |
| 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。 | ||
| ● | 純損失の繰越しと繰戻し | |
| 事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 |
|
|

