 |
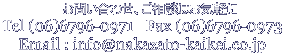 |
 |
||||||||
 |
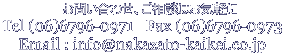 |
 |
||||||||

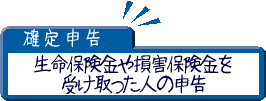
| 生命保険金や損害保険金を受け取った人 |
|
生命保険の死亡保険金や満期保険金を受け取った場合にはその保険の保険料を支払った人(保険料負担者)と保険金受取人の関係でいろいろな税金の対象となります。所得税の確定申告において申告しなければならないのは保険料を支払った人と保険金受取人が同一人物であった場合です。その他保険料負担者と保険金受取人の関係を図に示すと下記のようになります。 |
| 保険金 の種類 |
保険料 負担者 |
被保険者 | 保険金 受取人 |
税金の種類 |
| 死亡保険金 | A | A | Aの妻 または子 |
相続税 |
| A | A | B | 相続税 | |
| A | Aの妻 または子 |
A | 所得税 (一時所得) |
|
| A | Aの妻 |
Aの子 | 贈与税 | |
| 満期保険金 | A | − | A | 所得税 (一時所得) |
| A | − | Aの妻 または子 |
贈与税 |

|
|||||||||||||||||||||||||
| 高度傷害保険金、入院給付金、疾病により高度障害になったことが原因で支払われるものについては保険料負担者、受取人に関係なくその保険金受取人が被保険者の親族であれば非課税となります。 |
| 保険料負担金と保険金受取人の関係でかかる税金の種類が変わる | |
| 死亡保険金や満期保険金を受け取った場合に保険料負担者と保険金受取人の関係でかかる税金の種類が変わります。所得税の対象となるのは保険料負担者と保険金受取人が同一の人物である場合に限られます。このケースでは一時所得として申告することになります。 |
| 一時所得の計算 |
||||
| 一時所得とは他の所得に当てはまらず臨時に得た所得のことを言います。保険金の受け取りのほか、立ち退き料やクイズや懸賞の賞金、競馬・競輪の払戻金も対象です。一時所得の計算は収入金額から必要経費を差し引いた金額に特別控除額50万円をさらに差し引いて、その金額を2分の1した金額が一時所得の金額となります。 | ||||
|
| 非課税になる補償金 |
|
| 保険金や補償金の中には所得税が非課税のものがあります。交通事故にあってしまった場合や他人に原因があってけがをした場合にその加害者から受け取った見舞金や治療費である損害賠償金や、不慮の事故のために自分が契約していた傷害保険金を受け取ることがあります。このようなときに受け取った損害賠償金のうち心身または資産に加えられた損害に対して支払われるもの、さらに給付金で自己の身体に基づくものは非課税になります。また、所得補償保険により自分が就業不能である期間に応じて支払われる保険金や失業時に支給される失業給付金も非課税になります。 |
| 事業所得になる補償金 |
|
| 上記において所得補償保険による補償金は非課税と書きましたが、事業を営んでいる個人事業者が道路工事等で休業を余儀なくされてしまった場合にその休業期間の所得の補償として支払われる補償金については、その期間の収入を補てんするための補償金であり事業上の収益として事業所得の対象となります。また、借家に住んでいる人が立ち退き料を受け取ったような場合でも借家権の対価として受け取ったものは譲渡所得の収入金額として計算されます。 |
| 一時払いの養老保険 |
|
| 養老保険は一定の期間の間で死亡保険と生存保険の両方を兼ね備えた保険で、保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期を迎えた場合には満期保険金が支払われます。一時払い養老保険とは保険料を一回で支払うものです。この一時払い養老保険の中で保険期間が5年以下または5年以内に解約した場合には20%の源泉分離課税になりますので申告の必要はなくなります。ただし5年を超える保険期間のものについては一時所得の対象となり50万円を超える所得が発生した場合には確定申告をしなければなりません。 |
| 一時払いの養老保険 |
||
| サラリーマンで給与所得しかない人は給与所得以外の所得が20万円以下のとき申告不要になりますので収入金額から必要経費を引いた金額が40万円以下であれば申告はしなくてもよいことになります。 | ||
| 収入金額が120万円で必要経費が30万円の場合 | ||
|
| 年金形式で受け取った保険金 |
|
| 死亡保険金または満期保険金を年金形式で受け取った場合には雑所得、死亡保険金または満期保険契約金を年金形式で受け取った場合には公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金から、その年金に対する払い込み保険料の額を差し引いた金額になります。 |
|
|

