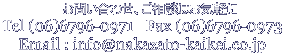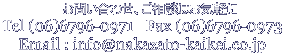税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類があり、私たちにはこれらを納付する義務があります。この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを確定申告といいます。
確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあります。したがって、確定申告は税金を計算し、払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。
確定申告をしなければならないのはどのような人でしょうか? まず、個人事業主は確定申告が必要というのが一般的でしょう。しかし、給与所得者、いわゆるサラリーマンであっても確定申告しなければならないケースがたくさんあります。
通常サラリーマンについては会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするしくみになっています。ただし、完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っています。
つまりサラリーマンは、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定するわけです。ただ、年末調整ではできない控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。年末調整ではできない控除を受けるため、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税を返してもらうことができるのです。 |